【じほうインタビュー】データと仮説から薬学を“読む”おもしろさ

薬剤師の武器は、薬の「構造式」や「データ」から仮説を立て、それを実際の患者ケアに活かしていく力にこそある。そんな視点で話題となった連載「構造式から読み解く くすりのプロファイル」が、「患者のデータ」という視点が加わり、このたび『薬効解析で調剤の視点が変わる説』として書籍化しました。「考える楽しさをもっと薬剤師に感じてほしい」と語る著者の黒木央先生に、本書の読みどころや、考える薬剤師になるヒントを伺いました。
「この患者に何をどう伝えるか」を考えるのが薬剤師の仕事
―― 本書では、薬剤師が患者との会話からヒントを得る場面が多く登場します。患者の話に耳を傾ける重要性について、どうお考えですか?
患者さんとの会話って、本当にヒントがいっぱいあるんですよね。僕が学生とか若手の薬剤師に向けた講義のなかで伝えているのは、「この患者さんに何をどう伝えるのがいちばんいいのか」って、そこを常に考えてほしいということなんです。
例えば書籍のなかでも登場するテーマですが、グレープフルーツジュースとの飲み合わせで、おばあちゃんに「これはOK、これはNG」っていう一覧表を渡しても、まず伝わらないですよね。だったら、「温州みかんは大丈夫だよ」って、その人にとってわかりやすいかたちで伝えてあげるほうが、よっぽど意味があると思うんです。
そういう意味で、「観察力」と「伝える力」って本当に大事だと思っています。マニュアルどおりじゃなくて、相手にあわせた服薬指導が求められているのではと考えています。
「構造式」のおもしろさをもっと身近に─連載と書籍の違い
――『調剤と情報』の連載をリニューアルするかたちで本書が生まれましたが、あらためて、今回の書籍の読みどころを教えてください。
予備校で講師をしていた時から「薬学は化学!」という言葉を使って講義を行っているのですが、薬剤師の職能の“核”って化学的な視点にあると思うんですよね。医療のなかで構造式をちゃんと読めるのって、薬剤師の大きな強みだと思っています。
でも実際、薬学部でも化学が苦手なまま卒業して薬剤師になる人って少なくない。だから、連載のときは薬をキャラクターに見立てて、構造式に対する心理的なハードルを下げる工夫をしてきました。
一方で、今回の書籍はもう一歩踏み込んで、患者さんとの会話や背景、検査値のデータから「この人にはこうしたほうがいいんじゃないか?」という“仮説”を立てて、それを検証して実行していく、というアプローチにこだわりました。 実際の調剤業務のなかでも自然とやっていることなんですけど、あらためて考えてみると、「仮説を立てて検証する」ってすごく大事なサイクルなんだな、って気づいてもらえると思います。そこに、薬剤師としてのおもしろさややりがいがあると思います。
知識整理のコツは「仮説を立てる」こと
―― 知識を整理し、実務に活かすコツがあれば教えてください。
これ、よく聞かれるんですけど、「整理しよう」って意識して整理したことって、僕は実はあまりないんですよね。簡単に言っちゃうと「センス」って言葉になりがちなんですが、それをちょっと掘り下げて考えてみると、仮説を立てて考えるっていう習慣に結びついているんじゃないかな、と思います。
例えば、ある薬の分布容積がそれほど大きくないときって、国家試験レベルの知識だと「脂溶性が高くないんだな」って理解するじゃないですか。でもそこで、「なんでこの数字なんだろう?」「本当に脂溶性が高くないの?」「そのままこの数字を受け取っていいの?」って、自然に一歩踏み込んで考えられるかどうか、そこが大きな違いだと思うんです。
背景をもうちょっとみていくと、「ここに水酸基があるけど、それで脂溶性は高くないのかな?」「タンパク結合率が高いからほとんど血中にいて分布容積が小さくみえているのかも?」みたいに、いろんな知識がつながってくるんですよね。薬物動態のパラメータ1つとっても、漠然と見ればただの数字になってしまうけど、少し踏み込んで考えると薬のキャラクターが見えたりするんです。
だから、知的好奇心とか探究心って、薬剤師という仕事のなかですごく大事だと思うんです。難しく考える必要は全然なくて、「ちょっと一歩踏み込んで考えてみよう」って意識するだけで、世界の見え方ってすごく変わってくると思いますよ。
―― 読者に向けて、メッセージをお願いします。
いま、薬剤師の活躍の場ってどんどん広がってきています。「かかりつけ薬剤師」って言葉も定着してきたし、これからはもっと患者さんと深く関わるチャンスが増えるはずです。
でも、そのなかで薬剤師の立ち位置をしっかり確立していくのは、やっぱりこれからの薬剤師次第だと思います。だからこそ、ぜひ化学的な視点や考える力を武器にして、医療のなかで薬剤師としての価値をどんどん発揮していってほしいと思います。
実は、書籍としては今回が初めての執筆だったのですが、執筆って思ったよりエネルギーがいるんだなと実感しました。いや、自分でもよくここまでまとめたなと思います(笑)。ただ、かたちになったことで、いろんな薬剤師さんに“考えるきっかけ”を届けられるんじゃないかなと嬉しく思っていますので、ぜひご覧いただければと思います。
大阪薬科大学(現 大阪医科薬科大学)卒。国家試験予備校講師として10年間勤務し、科目横断的な指導を行う。その後、調剤薬局にて薬剤師教育に従事。現在は「PharmAssist Lab」を設立し、薬学生教育、薬剤師学術研修、MR研修など幅広く活動している。
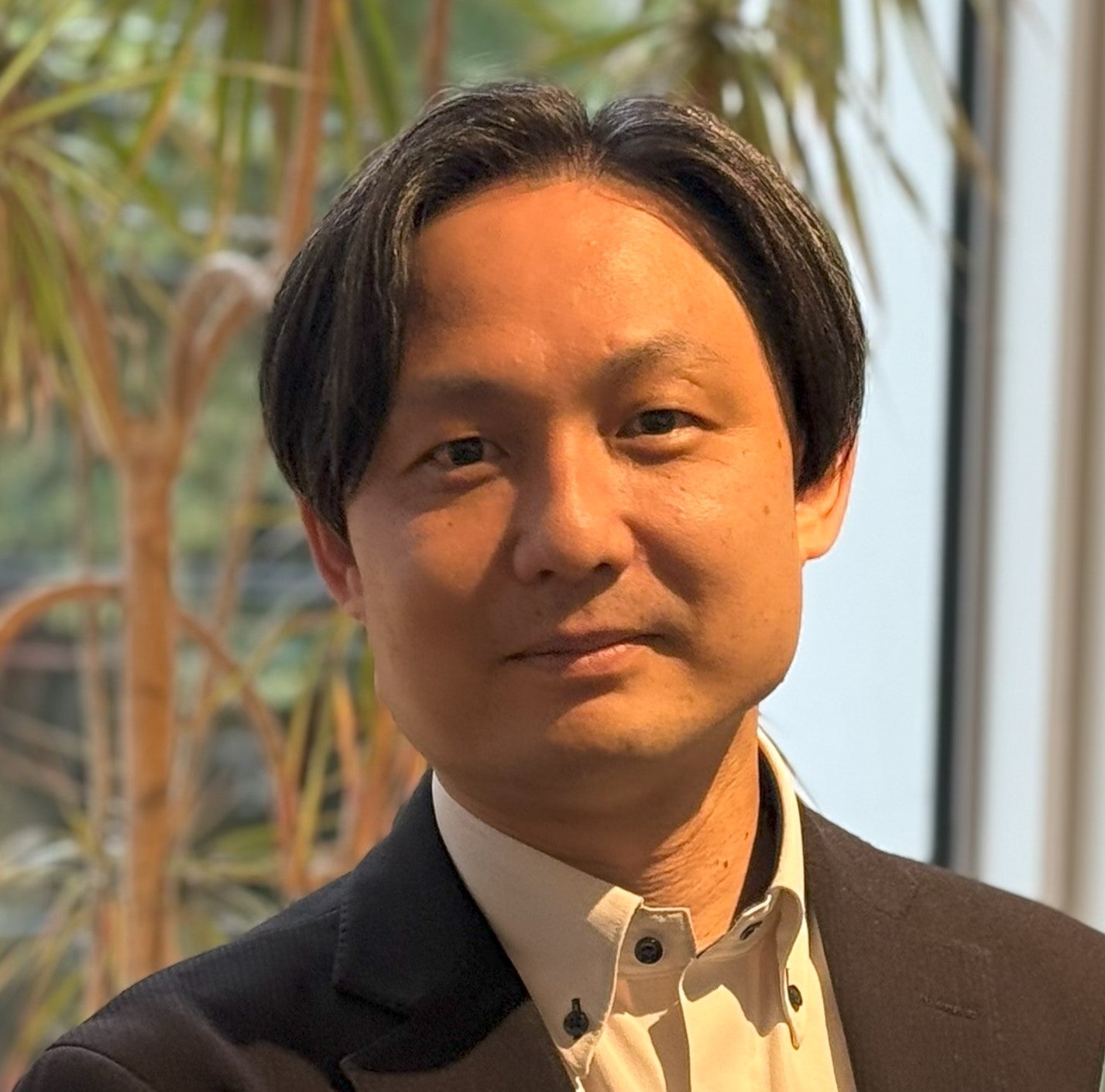

患者と薬物のデータから考察する
薬効解析で調剤の視点が変わる説
定価3,850円(本体3,500円+税10%)
構造式や添付文書、インタビューフォームに記載された数値から深掘り、すぐに調剤業務に活きる!
本書は、薬剤師が日々の業務のなかで抱くちょっとした疑問やひらめきを“●●説“として取り上げ、その根拠を患者背景や化学構造式、添付文書、インタビューフォームなどのデータから検討し、結論を導き出すという書籍です。調剤の現場で一度は経験する“あるある“や、時にはハッとするような気づきまで、新たな視点を得られる1冊です。
